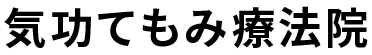人間の体の約60%~70%は水分で出来ています。
この水分と云うのは体液のことで、血液、リンパ液、組織液からなります。
怪我をしたときに透明な液体が出てきたことはありませんか?
これは細胞の周りにある栄養水「組織液」です。
採血した後、試験管の中で、半透明な液体が上澄みに出てきます。
これが「血漿・けっしょう」という成分で、この血漿が血管の外に染み出すと「組織液」となり、リンパ管に回収されると「リンパ液」となります。
リンパとは
リンパとは、人体の免疫システムに関わる重要な役割を果たしている液体と、それを運ぶ管(リンパ管)を指します。リンパ液は、血液からしみ出た余分な液体や老廃物を回収し、体の中の浄化システムとして機能しています。
主な特徴:
1,リンパ液: 無色透明で、細胞から排出された老廃物や異物を運びます。また、免疫を担うリンパ球などの細胞を含んでいます。
2,リンパ節: リンパ管の途中に点在する小さな構造物で、体内の浄化フィルターのような働きをします。異物や細菌を捕捉し、免疫細胞がそれを攻撃します。
3,リンパ管: リンパ液を運ぶ管で、体中に広がっています。
リンパの役割:
1,免疫機能: 体外から侵入してくる病原体や異物を除去し、感染を防ぎます。
2,老廃物の排出: 細胞から出た老廃物を回収して、静脈に戻します。
3,体液の調整: 体液のバランスを維持し、むくみの防止に貢献します。
リンパの流れが悪くなると、むくみや疲労感、免疫力の低下につながることがあります。そのため、リンパマッサージなどで流れを促進することが美容や健康維持に役立つとされています。
リンパは病気から体を守ります
リンパのネットワークがきちんとしていると、免疫機能が高まり、細胞の再生力が向上します。また、リンパには、体内のリンパ液を運び、体内の毒素・老廃物を排泄する作用があります。
病原菌から体を守る防御システム、それは「免疫機能」です。
リンパ節の役割は菌が体内に侵入して来ないようにまさに「関所」の役目をして、最終的に心臓や脳に菌が流れ込まないように、何重にもチエックが行われているのです。
免疫機能の他にもう一つリンパには大切な働きがあります。それはリンパが余分な老廃物を排出する「老廃物のろ過機能」です。
リンパ液の成分は
リンパ液の成分は、体の健康を維持する上で重要な役割を果たすさまざまな要素を含んでいます。以下が主な成分です:
1. 水分
リンパ液の主成分で、全体の大部分を占めています。
組織から余分な水分を回収し、循環に戻します。
2. 白血球(特にリンパ球)
免疫細胞として、体内の病原体や異物と戦う役割を果たします。
特にリンパ球は、ウイルスや細菌を攻撃する重要な働きをします。
3. たんぱく質
血液中から漏れ出たたんぱく質を回収し、静脈に戻します。
たんぱく質の一部は免疫系や炎症反応に関与します。
4. 脂肪(キロミクロン)
腸で吸収された脂肪を運び、血流に運ぶ役割を果たします。
食事から摂取した脂溶性ビタミンも含まれています。
5. 老廃物・異物
細胞が排出した老廃物や毒素などもリンパ液に含まれ、体外に排出されるよう運ばれます。
6. 細菌やウイルス(場合による)
感染が起きている場合、リンパ液の中に病原体が含まれていることがありますが、リンパ節でこれを捕捉し除去します。
リンパ液は、血液とは異なり赤血球を含まないため、透明や淡い黄色の液体です。その流れを促進することは免疫力の向上やむくみの解消につながるため、適度な運動やマッサージが効果的とされています。
リンパはゆっくり流れている
リンパの流れは実際に非常にゆっくりです。これは以下の理由によります:
1. ポンプ機能の欠如
リンパ液は血液のように心臓という強力なポンプで循環させられるわけではありません。リンパ液は筋肉の収縮や血管の脈動、周囲の動きによって流れています。そのため、自然に動く速度が遅くなります。
2. リンパ管の構造
リンパ管は細く、壁も血管より薄い構造をしています。また、リンパ液には一方向に流れる弁があり、これが流れを管理していますが、一度に流れる量は少なく、全体的な速度が緩やかです。
3. 役割に合わせた流れ
リンパ液は老廃物や異物、脂肪を運搬し、浄化する役割を担っています。このプロセスは時間がかかるため、あえてゆっくりと流れるのが自然で効率的です。
4. 体液の量とリンパ節の働き
体中を巡るリンパ液は、リンパ節を通るたびに浄化・濾過されます。この濾過プロセスに時間がかかるため、全体の流れが緩やかになります。
このため、リンパの流れを促進するためには適度な運動やマッサージが役立つとされています。筋肉の動きや深い呼吸がリンパ液をスムーズに流す助けとなり、むくみの解消や免疫力の向上に寄与します。

血液とリンパ液の役割の違い
血液とリンパ液はどちらも体内を循環する重要な液体ですが、それぞれ異なる役割を果たしています。以下はその違いをわかりやすく説明した内容です:
血液の役割
1,血液は主に心臓をポンプとして全身を循環し、酸素や栄養を運ぶ働きをしています。
2,酸素と栄養の運搬: 肺で取り込んだ酸素を全身の細胞に届け、消化器官で吸収した栄養素を運搬します。
3,老廃物の除去: 細胞で使用された酸素や栄養によって発生する二酸化炭素や代謝産物を回収し、体外へ排出します。
4,免疫と防御: 白血球などの免疫細胞を運搬して感染や病原体から体を守ります。
5,体温調整: 体全体の温度を均一に保つ役割があります。
リンパ液の役割
1,リンパ液は血液に比べてゆっくり流れ、免疫と老廃物の回収に特化した働きをします。
2,老廃物と異物の回収: 組織液から細胞の老廃物や不要な物質を回収します。
3,免疫のサポート: リンパ球という免疫細胞を含み、病原体の除去や感染の防御に貢献します。リンパ節で細菌やウイルスを取り除くフィルターの役割があります。
4,脂肪の運搬: 腸で吸収された脂肪をリンパ管を通じて血液循環へ運びます。
5,体液バランスの維持: 余分な体液を回収して循環に戻し、むくみを防ぎます。
血液とリンパ液の役割の違いのまとめ
血液は酸素や栄養を供給し、老廃物を排除する「輸送の主役」で、全身を速く循環します。
リンパ液は免疫や老廃物回収、脂肪運搬に特化した「浄化のサポーター」で、比較的ゆっくり流れます。
どちらも体の健康を維持する上で欠かせない存在ですね。
リンパの流れを良くして細胞を活性化
長時間のデスクワークや立ちっぱなしなどでふくらはぎがパンパンにむくんでしまうことが無いでしょうか?「むくみ」は本来、リンパ管に回収する筈の組織液が、回収されずに残っている状態です。だから、「むくみ」を解消するには体を動かして筋肉を収縮させたり、リンパ管に外からの力を加えたりして、滞ったリンパ液の流れをよくしてあげれば良いのです。ストレッチやマッサージなどで筋肉を動かしてあげると、リンパ管が刺激され、リンパの流れも良くなります。
リンパの流れが良くなると、たんぱく質などの栄養素が細胞に行き渡り、臓器の動きが改善されるなど、新陳代謝が良くなります。
ストレッチやリンパマッサージは、自分の手だけで、細胞レベルにまで働きかけて新陳代謝を促す、最高の健康美容施術になるのです。
このリンパをサラサラにする秘密はリンパデトックスと骨格矯正の組み合わせにあります。
脊髄の束が通っている背骨と骨盤のゆがみはリンパの働きを司る自律神経の機能を阻害するうえ、筋力(リンパ液を全身にへと送り出すポンプの役割)を衰えさせます。
神経の集まる場所にツボはある
「経絡」とは「気」の通り道です。経絡は全部で14経あり、それぞれの経路の要所にあり、「気」の流れを調整しているのが「経穴」、いわゆる「ツボ」になります。
東洋医学では、「邪気」と呼ばれる邪悪な気が体内に入り,「気」のめぐりが悪くなると病気になると考えられています。たとえば「経絡」を神経やリンパの流れとして、「邪気」をバイ菌やウィルスと置き換えてみると理解がしやすくなると思います。
約3,000年も前に「神経」や「脳のメカニズム」、目に見えない「ウィルス」の存在が明らかにされていない頃に「気」という言葉を使い、病気を治し、病気にならない「予防」を手に入れたのですから、本当に凄いことだと思います。
気功てもみ療法院は、「気」の滞りをツボを押して流し、併せてリンパを流すことでお身体の悪い状態を短時間で良くします。リンパデトックスと骨格矯正も行うことによって徹底した毒素排泄を促しています。
気功てもみ療法院の気功リンパ整体療法を是非、お試しください。

ピラティスとは、
ピラティスとは、1883年にドイツで生まれたJoseph Hubertus Pilates(ジョセフ・ハベルタス・ピラティス)氏によって考案されたエクササイズです。
自分自身が様々な病気を持病としてもっており、その病弱な身体を克服するために様々なスポーツや治療法を研究し、それらの組み合わせたものがピラティスの原形だと言われています。
体幹(インナーマッスル)を鍛え、姿勢を改善し、全身のバランスを整えることを目的としています。
ヨガと似ていますが、ピラティスは特に体幹の強化や動きの質を重視する点が特徴です。

ピラティスは、もともと負傷した兵士のリハビリのために開発されましたが、現在では健康維持や美容、スポーツパフォーマンスの向上を目指す多くの人々に利用されています。
ピラティスでは、インナーマッスル(体幹)を育てて、安定に導く方法はシンプルです。
まず、頭を正しいポジションに置きます。
その上で首と背中を伸ばしながら動くのです。これがピラティスの基本になります。
ピラティスでの呼吸は、交感神経を活性化させる胸式呼吸が基本です。
息を吸う際にはしっかりと肋骨を広げて、たくさんの酸素を取り込みます。
胸式呼吸で胸に空気を深く吸い込むと、肋骨の下に付いている横隔膜やお腹周りのインナーマッスルである腹横筋、そして、骨盤で内臓を支えている骨盤底筋までもが動きます。
すると、内臓の細胞を刺激することができるため、活性化されます。

ピラティスの効果
姿勢の改善
背骨や骨盤、肩甲骨や股関節などを意識し、「正しく動かす」ことを学ぶことにより、身体が機能しやすい自然な位置に骨や内臓を配置する力を鍛えます。
頭、首、背中の正しいポジションを意識しながらエクササイズをするとインナーマッスルが鍛えられ、姿勢が改善されるのです。すると、体が正しく動くようになります。
一つひとつの背骨の間にある細い筋肉を強化することで、背骨を正しい位置に置く力を強化し、常にアライメント(左右のバランスの確認)を行うことで、歪みのないバランスの取れた筋肉を作り、美しい姿勢に導きます。
インナーマッスルの強化
体の表層部には、自分の意志で動かすことが可能なアウターマッスルがついていることは知られています。一般的に、スポーツジムでのウエイトトレーニングや筋トレで鍛えるのは、このアウターマッスルです。
ピラティスでは、手では触ることができない場所にある深層筋のインナーマッスルを重視します。動きと共に呼吸を使い、体幹部にあるインナーマッスルを強化していきます。
インナーマッスルを育てて、安定に導く方法はシンプルです。まず、頭を正しいポジションに置きます。その上で首と背中を伸ばしながら動くのです。これがピラティスの基本になります。
骨盤の底面にハンモック状に存在する「骨盤底筋群」、 お腹の周りをコルセットのようにぐるりと囲む「腹横筋」、背骨を支える脊柱起立筋の深層部に位置する「多裂筋」、そして腹腔の上部分を覆い呼吸と共に動く「横隔膜」 の4つの筋肉を合わせた「インナーユニット」を、呼吸の使い方によって鍛えていきます。
自身の免疫力を高める
免疫力を正常な状態に保つには、ストレスのコントロールと腸内環境を整えることが大切です。脳の一部にストレスが過剰にかかると、脳全体の機能や、 免疫に関わるホルモン系や自律神経系の機能にも影響を及ぼすことが理由です。
ピラティスは呼吸法と「集中」による瞑想効果(マインドフルネス)により自律神経をコントロールしていく事から、ストレス解消につながります。ストレスの解消はホルモンバランスを正常化させ、それは内臓機能を正常化させます。
ストレスの解消・睡眠の質向上
ピラティスでおこなう胸式呼吸は交感神経に働きかけ、頭や身体を活性化させる効果を持ちます。レッスン後に頭がすっきりとする爽快感を得られるのはこのためです。

呼吸とリズムを伴う動きでは、良質な睡眠に欠かせない「メラトニン」というホルモンの原料となる、「セロトニン」の分泌を増やします。そのため、日中にピラティスを行うことで、睡眠の質が向上する効果も期待できます。
ホントに良く効くリンパとツボの本 加藤雅俊書 参照・引用 ・ ツボ、リンパマッサージの本参照
zen place ブログ参照・参考・引用・キャリカレブログ参考・参照・引用